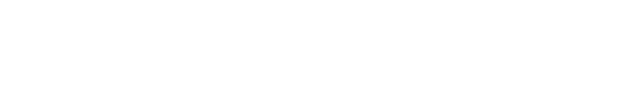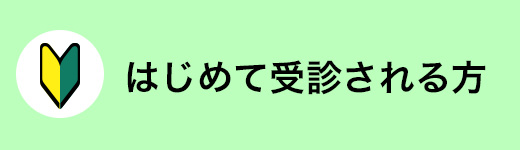カウンセリングの分類と比較
[2024.12.05]
カウンセリングの分類と主要理論の比較
下表は、諸富祥彦先生による、カウンセリングの主要理論の比較表です。
表 カウンセリングの主要理論比較表
自己成長論 |
精神力動論 |
認知行動論 |
|
代表的な立場・理論 |
来談者中心療法 |
精神分析 |
認知行動療法 |
クライアント(患者)理解の枠組み |
内面を内側から理解する。 |
内面の深いこころの動きをもう少し外側から理解する。間主観から理解する。 |
外面を外面から理解する。 |
リアリティをどうつかむか |
現象学 |
心的現実 |
データによる実証 |
主観と客観 |
主観 |
間主観 |
客観 |
主に、何に着目するか |
「固定化し変化に抵抗する要因」と供に、「今、新たに浮上してきている内的体験」に着目する。 |
「人生のつまづきや人間関係の失敗の反復されるパターン」および「セラピストとの関係におけるその再現」に着目する。 |
反復されるマイナスの「思考・行動・注意の向け方」のパターンおよび「その前後にあって、それを引き起こし維持させている要因」に着目する。 |
理解の方法 |
傾聴クライアントになりきって、その内面世界を内面から理解する。 |
転移・逆転移過去の生育史がセラピストとの関係にどのようなパターンとして反復されているか。 |
観察/自己観察データの取得「思考・行動・注意の向け方」の反復されるパターンを見て取る。 |
理論モデル |
目的論 |
因果論 |
因果論 |
人間観 |
実現傾向人間は成長への志向性を持っている。 |
生物学的人間観人間はエロス(生の本能)と死の本能(タナトス)に引き裂かれている。 |
人間は習慣の束である。習慣は、刺激(S)と反応(R)の結合によってつくられる。 |
パーソナリティ論 |
「自己概念」と「有機体的体験」との一致・不一致体験様式の変化 |
自我・超自我・イド意識・前意識・無意識 |
刺激と反応の結合が行動誤って学習された「不適切な思考・行動・注意の向け方のパターン」が不適応の原因 |
カウンセラーの役割 |
自己探求の道の「同行者」 |
両親への怒りや憎しみを投げ入れられる「器」 |
「思考・行動・注意の向け方」を自分で制御できるようになるための「トレーナー」 |
代表的な技法 |
リフレクションエンカウンターフォーカシングエンプティチェア |
転移や抵抗の分析解釈ワークスルー夢分析 |
エクスポージャースモールステップ自動思考の記録マインドフルネス |
想定されるクライアント(患者)の変化 |
実存的自己探求体験をじゅうぶんに体験する。体験のプロセスの前進的展開 |
過去についたこころの傷や「人生や人間関係で反復されるパターン」からの解放 |
「適切な思考・行動・注意の向け方」を練習することで獲得する。(再学習) |
目指す方向 |
生涯にわたり「自己探求」「人生の意味・使命」の探求「それに伴う、自己の深まり・高まり・拡がり」の体験 |
深い「洞察」の達成人格の成熟 |
自身の「思考・行動・注意の向け方」を注意深く「自己観察」し「自己制御」する人間自身の心身の健康を「自己管理」できる人間 |
慢性の痛みの心理療法を選択する場合は、カウンセリング全体を見渡し、十分に理解した上で、
慢性の痛みを抱えた患者さんと、治療者が、何を目指していくのか明確にし、
医療面接(医師、看護師、理学療法士、作業療法士などの医療者が行う身体的、心理的、社会的、実存的カウンセリング)を行うことが重要だと考えています。
諸富祥彦:カウンセリングの理論 上編 -三大アプローチと自己成長論-. 誠信書房, 東京: pp32-33, 2022
永田勝太郎:実存カウンセリング. 駿河台出版社, 東京, 2002