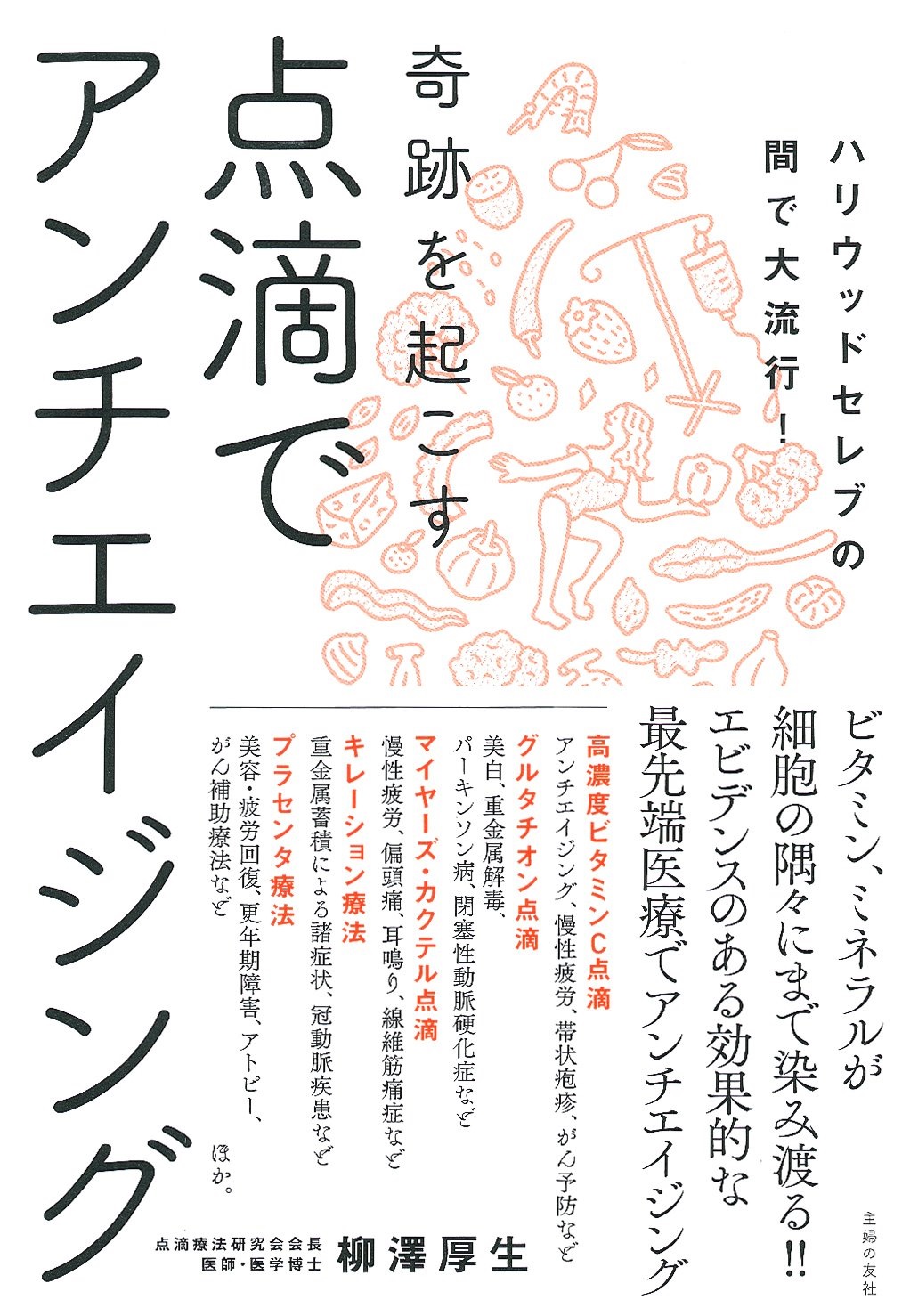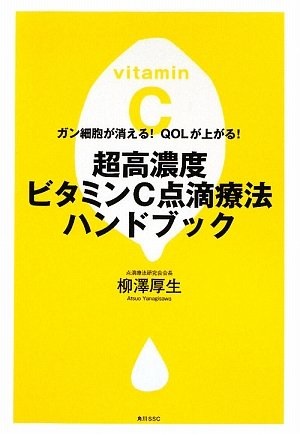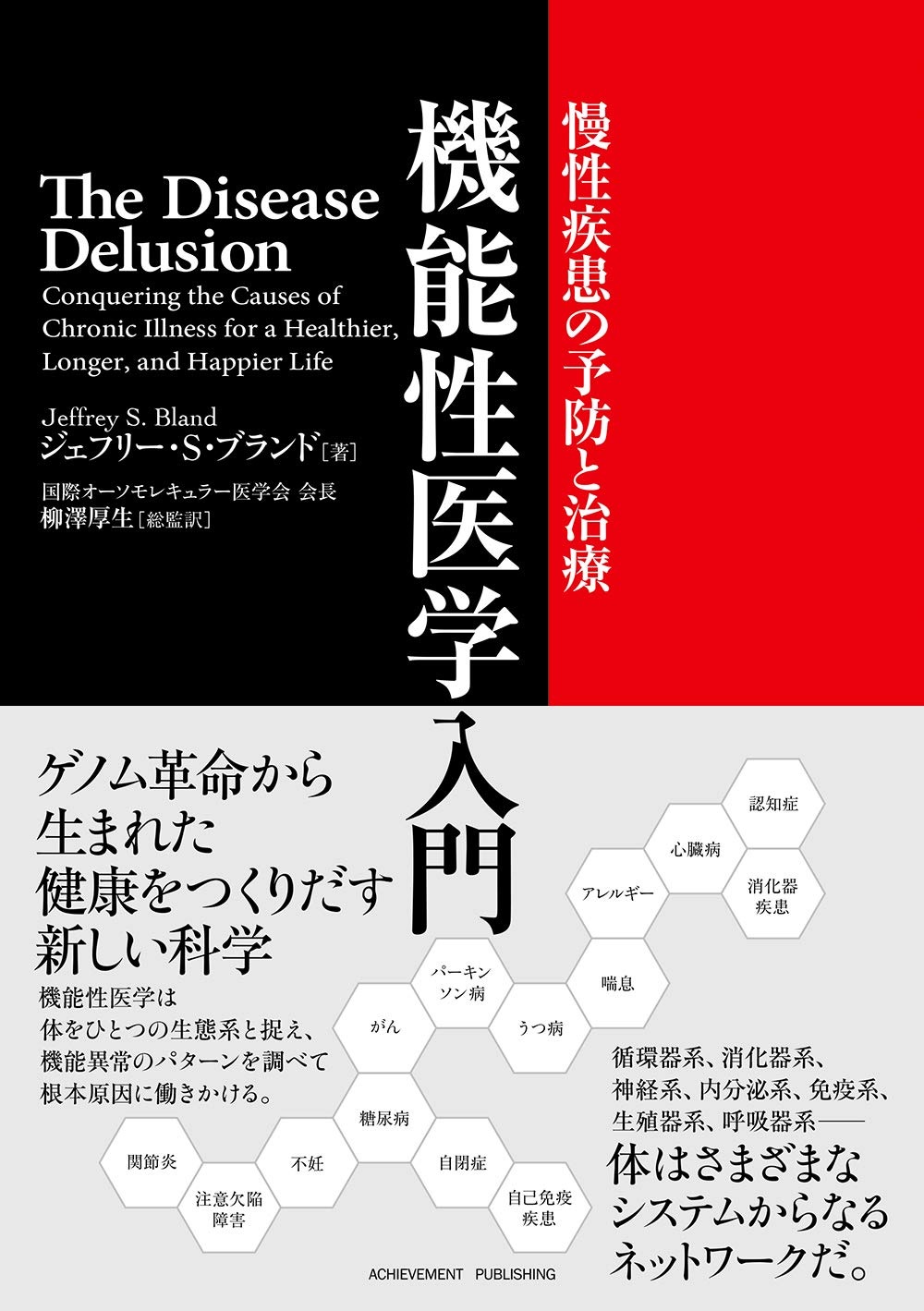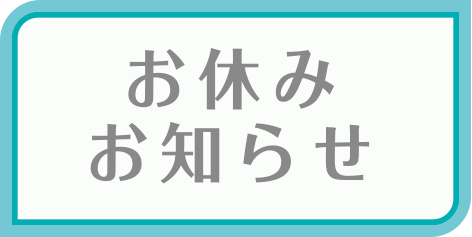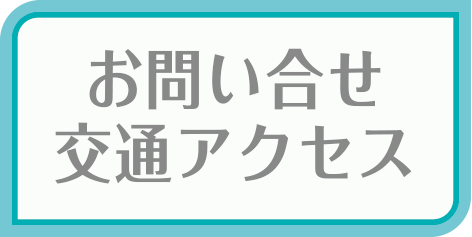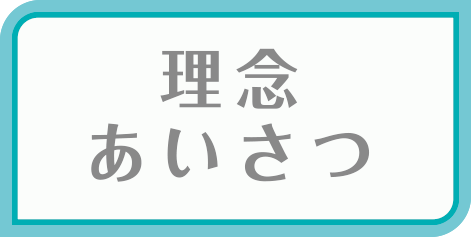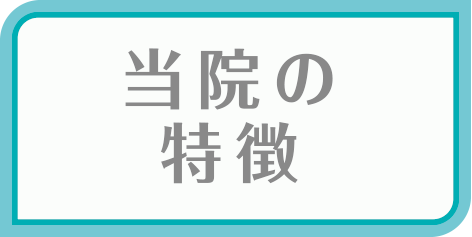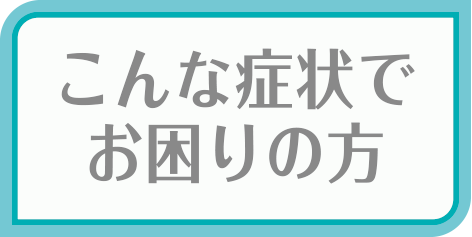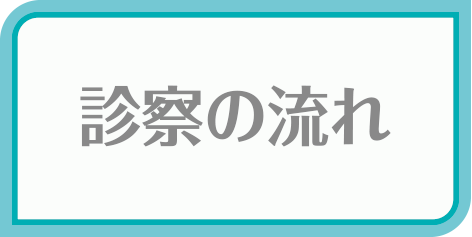痛みと疲労の治療
本ホームページでは、痛みと疲労の中心の疾患あるいは病理を特発性(idiopathic)・小径線維ニューロパチー(iSFN)との前提で捉えます。
そしてiSFNに対する治療の概念は、
異常興奮、損傷もしくは退化した小径線維(Aδ線維、C線維)を回復もしくは再生させるために、
1,正常もしくは治療的な血液成分にすること。
2,全身臓器の微小循環を整えること。
と考えます。
そして、この2つは、
ホメオスタシスの歪みを回復させること
につながります。
初期(initially)のiSFN(iiSFN)はこの治療法で回復する可能性のあるiSFNです。
上記の治療概念による治療は、この段階のiSFNに対して、最も適していると考えています。
末梢性感作および中枢性感作を来たし、認知の歪み、愛着障害の表面化等の心理的偏りが出現した、難治性のiSFNを来して患者さんに対しては、この治療法の効果は小さいと考えられます。それに対しては、それらに対する治療法を加えなくてはならないと考えています。
当院では、残念ながら、このような難治性iSFNの段階の患者さんを診療することに対して、当院のスタッフ(整形外科医師、看護師、理学療法士、鍼灸師など)による専門横断的(transdisciplinary)チームアプローチでは力不足です。滅多に投与しませんが、対症療法的に、ホメオスタシスへの悪影響を考慮しながら抗てんかん薬(リリカ、タリージェなど)、抗うつ薬(サインバルタなど)などの薬物治療を行う程度です。漢方治療も行っています。
精神科医、臨床心理士、ソーシャルワーカー、ペインクリティシャンなどを加えた多職種の集まることのできる大学病院、総合病院あるいは痛みの専門に特化した一部のクリニックなど、痛み治療の集学的(multidisciplinary)もしくは学際的(interdisciplinary)な治療を行っている医療施設が適当と考えます。
しかし、iSFNに対する治療法は、どの治療法を選択するにしても、中心となる、あるいは考慮すべき治療法と考えています。
後天性(acquired)、遺伝性(hereditary)、症候群性(syndromic)による小径線維ニューロパチー(SFN)は、各専門分野の領域であり、
当院は、整形外科および心身医学(専門横断的)アプローチが基本専門分野のため、これらの疾患によるSFNの治療はできません。
当院の治療環境で可能な、iSFNに対する治療法は、
① 治療に適した、より良き関係を築く(相互主体的関係)
② コンセンサスを得られている診断基準による診断
③ 食事療法
④ サプリメント療法
⑤ 点滴療法
⑥ 漢方治療
⑦ 対症的薬物治療
⑧ 起立不耐症を合併した方への治療
⑨ 鍼治療
⑩ リハビリテーション
⑪ 上記以外の身体的治療
⑫ 経過中のこころを支える
⑬ できる範囲で社会的支援を行う
⑭ 信頼できる、信頼できそうな他院へ紹介する
以上です。
★ 痛みと疲労の疾患、特にiSFNに対する確立した治療法はありません。また、当院においては治療法に関してのオリジナルな研究はしておりません。特に、私をはじめ医療スタッフの技術や知識が特別優れているいるわけでもありません。
この分野は、世界中の素晴らしい医療者たちが、試行錯誤し、さまざまな研究を行い、少しでも苦しんでいる患者さんの症状が改善するように情熱を傾けています。
当院の治療の中心は、その方々の研究や臨床経験に基づいた書籍や研究報告を少しでも皆さんに紹介することです。
また、ご自分で調べ、その内容を実践し的確な治療を行っている方もいらっしゃいます。
私のほうが教えられることも多々あります。
オーソモレキュラー療法、分子整合栄養学、点滴療法、機能性低血糖、漢方医療、副腎疲労、機能性医学、腸内細菌などで検索すると、様々な医療機関がヒットします。
そのような医療機関は、iSFNが発症するホメオスタシスの歪みに対して、当院よりはるかに多くの治療法をそなえています。また、世界中のどなたかが、少しでも症状が軽くなる方法とご存じかもしれません。
本ホームページは、当院での治療内容よりも、医学情報の提供を主としています。
皆さまの近隣にもより多くの治療が可能な医療機関がある可能性があります。
検索してみてはいかがでしょうか。
治療に適した、より良き関係を築く(相互主体的関係)
診断と治療がほぼ確定している専門分野の疾患と異なり、痛みと疲労の確立された治療法はありません。
患者さんやご家族は、当然これらの病気により辛い思いをしています。
そして痛みと疲労に立ち向かうことを決意した医療者も、専門分野にはない診療の困難さや社会(同業であるはずの医師、国や地方公共団体、勤務先の会社、学校、時に患者さん本人、時に患者さんのご家族)との大きな軋轢に疲弊し、極限の精神力を発揮しなければならない道を歩むことになります。
この辛く長い治療の道は、一方的に依存せず、一人の人として互いに相手をいたわりながら、良好なコミュニケーションで創り上げた、より良き(相互主体的)関係の元でしか乗り越えられません。
痛みと疲労の疾患に罹患した方々が健康へ向かう自己コントロールができるようになり、治療経過の中で人間的成長を得、より良き人生を歩んでいくことを願い診療を行っています。
コンセンサスを得られている診断基準による診断
線維筋痛症(FM)、筋痛性脳脊髄炎/慢性疲労症候群(ME/CFS)などの疾患は、苦悩が大きい割には、医師をはじめとする医療者や周囲の理解が得られず、かえって、心理的。精神的問題にすりかえられ、周囲から傷つけられている患者さんの多い疾患です。
この方々に、自分の専門分野の境界を超越し、世界的にコンセンサスを得られている診断基準に照らし合わせて、きちんと診断することは、医師のみが可能な、最も治療的な行為と考えられます。
事実、何年も苦しんだ方々が、診断されただけで心が救われることを多数経験しました。
本ホームページにFMおよびME/CFSの診断基準を載せています。
★人間は、どんなに重要なことでも見たい物だけ見ようとする心理(選択的認知)があります。専門分野にとらわれることは、選択的認知を繰り返し、自分の専門分野の症状には大きな価値があり、他の専門分野の症状には価値が小さい、還元的思考(人は~でしかない)を強化することになります。そして次第にwhole person(人間には専門分野という境界はなく全体的な存在)という視点から遠ざかっていきます。
そして行き着く先はどのような重要なことでも見えなくなる心理的盲目(スコトマ)の状態です。本当に見えなくなると、自分(医師)の視点の偏りのせいで人が不幸になることがあります。
食事療法・サプリメント療法
疾患は、時に脆弱性要因をもつ患者さんに、慢性のストレッサー(生活習慣の乱れ:不適切な食事内容、過度な飲酒、喫煙、睡眠不足、心理・社会・実存的ストレス)が加わると発症します。小径線維(Aδ線維とC線維)は、それによる血液成分の変化、十分な血液の供給不足などがあると、真っ先に興奮性の変化、神経機能の低下を来たし、痛み、しびれおよび疲労などの症状で脳に情報を伝えようとします。(本ホームページ、身体的苦悩BDと慢性機能障害性苦悩CDBDより)
慢性のストレッサーのうち、食生活の乱れは生物としての人間の健康を脅かします。食事療法は痛みと疲労にとって最も基本となる治療と考えます。
食事療法も確立されたものはありません。しかし、さまざまな優れた医療者の方々が数々の書籍などによって発信しています。
私が参考にしている、方々のできるだけ最新または代表的な書籍をご紹介します。
永田勝太郎著作シリーズ
著者は、40年以上、慢性の痛みの研究を行っていた、我が国の第1人者といっても良い存在です。
現在の痛み、疲労の臨床の世界は、抗うつ薬、抗てんかん薬などの痛みが治療法が隆盛ですが、
著者は、それらを中心にした痛みや疲労の治療に警告を発しています。
最初から、痛みや疲労の病態の中心は、ホメオスタシスの歪みが痛みと疲労の原因であると述べ、研究と報告を行ってきました。
30年前からコエンザイムQ10が、痛みと疲労の治療の一部に有益であると主張してきました。
さらに、心身医学の分野で、身体的、心理的、社会的なアプローチに、実存的な次元を加え全人的な医療を提言を行ってきました。
患者観察に優れ、先見の明があり、専門性の境界にこだわらず、慢性疼痛や慢性疲労が見向きもされなかった時代から多くの患者を救ってきた著者は、当時から現在まで、従来の医療に対するフロンティア精神と挑戦的な態度から反って医療世界の多くの方々からの理解が得られないことが多々あり苦難の道を辿っていました。
痛みと疲労の臨床において、著者の提言は、いつも2、30年ほど先を行っていると感じています。
各著書は、著者の多くの分野への造詣の深さにより、様々な分野が入り交じり著者独特の表現法となっています。
慢性の痛みと疲労の方で、低血糖、血糖値スパイク、起立不耐症(低血圧など)が潜んでいる患者さんに一読していただきたい著書です。
ただし②③④⑤は絶版となっています。中古品等でしか購入できません。
①と②のみでも十分な情報が得られます。
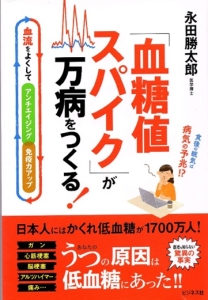
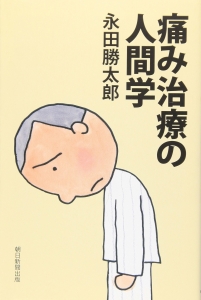
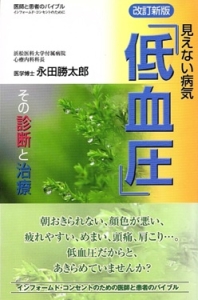
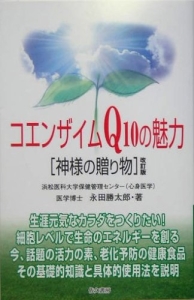
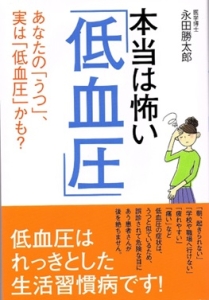
①「血糖値スパイク」が万病をつくる!. ビジネス社, 2020
この本は、機能性低血糖、血糖値スパイクが明らかに潜んでいる痛みと疲労の患者さん向けです。
痛みと疲労をあくまでもグルコスタシス(血糖調節機構)の視点から観たものです。
小径線維ニューロパチー(SFN)の大きな要因の1つにグルコスタシス(血糖調節機構)の歪みがあるため、一読をお勧めします。
痛みと疲労の患者さんは、糖質制限食で反って調子が悪くなることがあります。
そのことに警告を発しています。
②痛み治療の人間学. 朝日新聞出版, 2009(絶版)
②は著者が痛みと疲労の要因に、低血糖や血糖値スパイクが存在することを認識する前に発行された書籍です。
著者の人の痛みに対するゲシュタルト(全体像)が分かります。独特の表現があり、難しい箇所もあるかもしれません。
何度も、何度も、読み込んでいくうちに、自分の専門性(整形外科、ペインクリニック等)を包括した、著者に近づいたスキーマができあがっていきます。
③本当は怖い「低血圧」. 秀和システム, 2016(絶版)
④見えない病気「低血圧」. 佐久書房, 1995(絶版)
⑤コエンザイムQ10の魅力[神様の贈り物], 2003(絶版)
③から⑤の本は、いずれも絶版となっています。
いずれも起立不耐症(起立性調節障害)が、痛みと疲労に潜んでいること、
そして、その治療法が書かれています。
いずれも、良い本でしたので残念です。
①では、低血糖と起立不耐症の関係などが記載されています。
溝口徹著作シリーズ
柏崎良子著作シリーズ
藤川徳美著作シリーズ
三石巌著作シリーズ
金子雅俊著作シリーズ
点滴療法
点滴療法は、線維筋痛症(FM)や筋痛性脳脊髄炎/慢性疲労症候群(ME/CFS)などの痛みと疲労の方々の一部に、即効的に実感する治療法です。時に、点滴中から症状の変化が訪れる方々がいます。
特に、マイヤーズカクテル、高濃度ビタミンC、グルタチオンの点滴療法は、抗酸化作用、栄養補充療法として非常に有益であると実感しています。
まず、本邦の点滴療法の第一人者である柳澤厚生先生の著作が、一読するのに最も良いのですが、何故か、ほとんどが絶版となっており手に入りにくい状況です。
点滴療法研究会のホームページや、点滴療法を行っている医療施設で詳しく述べられています。
柳澤厚生著作シリーズ